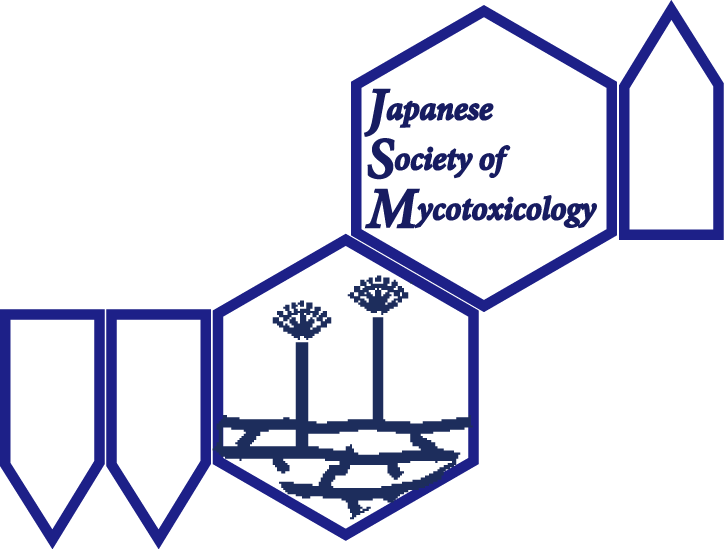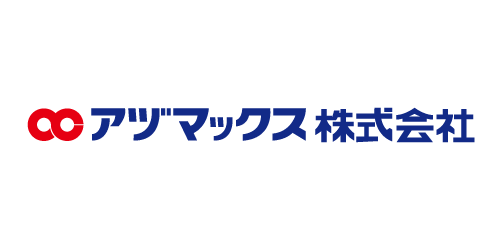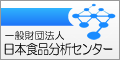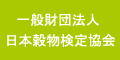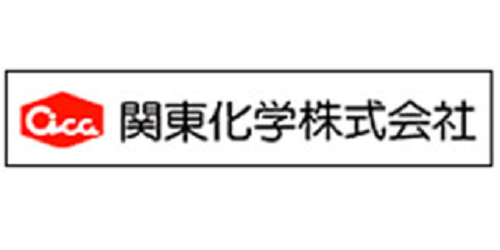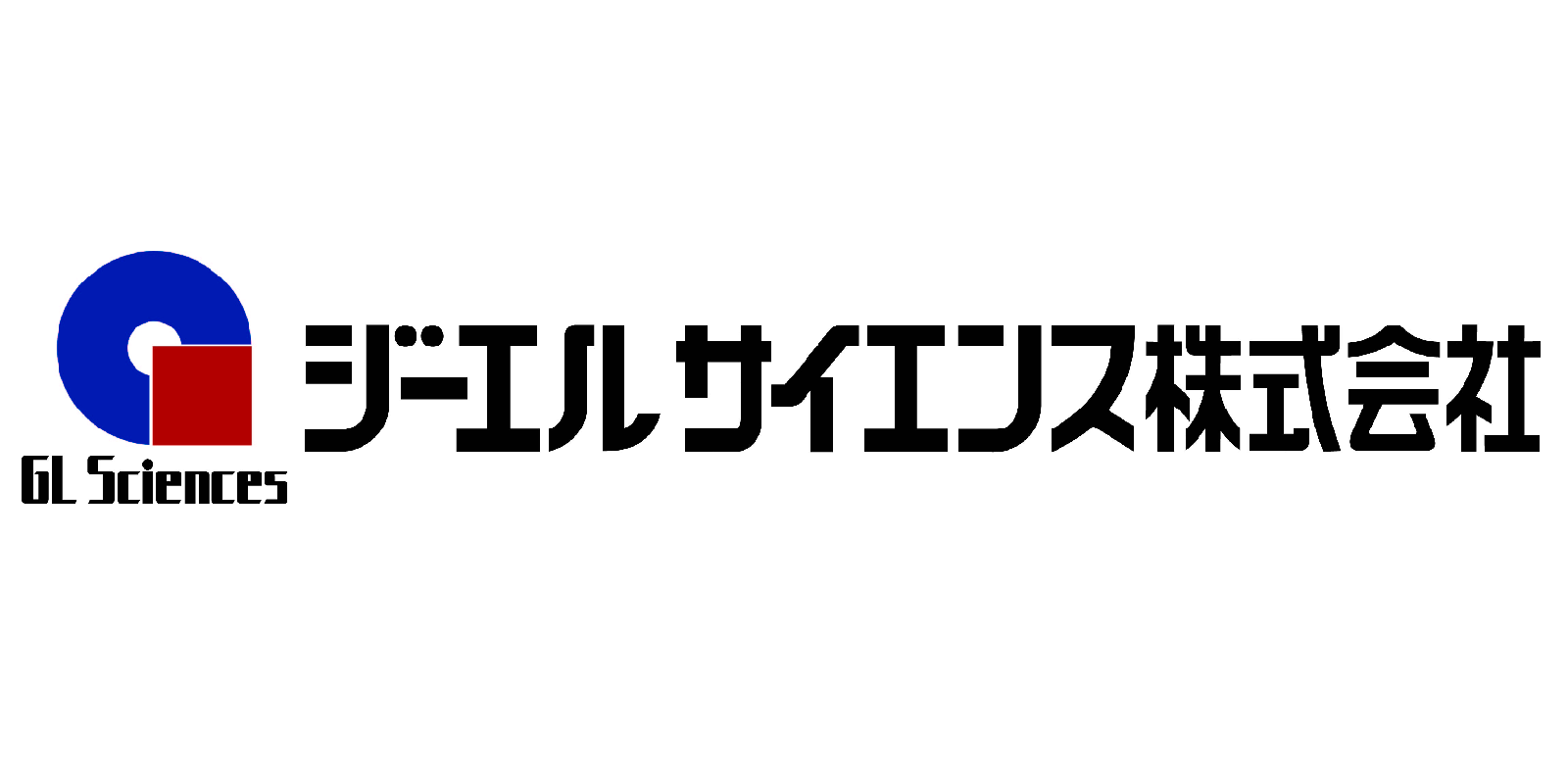会長挨拶
日本マイコトキシン学会は、農作物、飼料および食品に混入するかび毒に関する最新の研究成果や施策情報を提供し、安定した食糧供給に役立つ科学的知見を提供することを目的に活動を行っております。本学会の前身となるマイコトキシン研究会が発足した1974年から数え、ちょうど50年の節目を迎えることになります。この間、生命科学をとりまく研究環境や世界情勢は激変し、マイコトキシン研究も新しい時代の潮流の中で、次の50年に向かって進むべき新たな道を探索していかなければなりません。この大きな節目の時期に本学会の会長をお引き受けすることになり、その使命と責任の重さを痛感いたしております。
 日本マイコトキシン学会会長木村 真
日本マイコトキシン学会会長木村 真 さて、ホームページをご覧頂きますと、本学会のルーツは1970年代初頭の厚生省ガン特別研究のうち、カビ毒による発癌研究を担当した班活動に行きつく、と記載があります。当初、100名ほどの参加者で始まったマイコトキシン研究会が、発展的に解消して今日にまで至っているわけです。特別研究が終了して予算的な支援がなくなっても、その交流、活動が途絶えることなく続いてきたのは何故でしょうか?研究会が存続し学会へと発展したのは、すでに戦前から戦後にかけての黄変米研究において健康障害、深刻な疾病の原因としてかび毒を捉え、異なる専門分野の知識・価値観を融合させることによって世界のマイコトキシン研究をリードしてきた先達の先生方のマイコトキシン研究に対する情熱と実績があったからではないかと、私は考えております。その思いが後代の先生方にも受け継がれ、熱い討論を積み重ねてきた場として今日までの50年もの間、繋がってきたのでしょう。しかし研究会が発足する1970年代にかけて、我が国の研究者が世界のマイコトキシン研究の黎明期を開拓する上で大きな役割を果たしてきたことは、国内外の若い世代の方々にはあまり認知されていないようです。このような歴史と伝統を大切に伝え、本学会が今後取り組むべき活動について皆さんと一緒に考え、実践して参りたいと思っております。
本学会は、毎年開催される学術講演会および学会誌 JSM Mycotoxins を通じ、マイコトキシンおよび関連する幅広い研究領域で、基礎研究や応用研究の成果、安全性評価や指針策定の情報、および実践的な技術普及活動等を提供しています。関連省庁傘下の研究・試験機関に加え、大学や賛助企業の方々にも積極的に学会活動に参画して頂いており、様々な専門性、価値観をもつ非常に多様な会員から成り立っています。学会での様々な交流を通じて得られる情報や刺激を、ご自身の研究や技術開発に大いに活用していただけるような機会を増やし、社会に貢献できるよう最大限努力してきたいと思っております。どうか会員の皆様のご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
◆ 過去の会長の挨拶
作田 庄平 [平成28年(2016年)〜令和5年(2023年)]